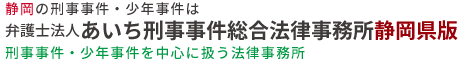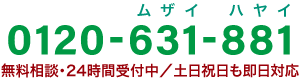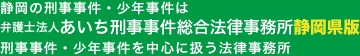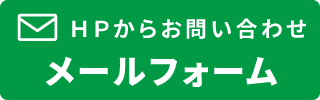Archive for the ‘財産犯罪’ Category
(事例紹介)窃盗の疑いで逮捕・送検された静岡市内の男性を静岡地検が不起訴にした事例
(事例紹介)窃盗の疑いで逮捕・送検された静岡市内の男性を静岡地検が不起訴にした事例

窃盗の疑いで逮捕・送検された静岡市内の男性を静岡地検が不起訴にした事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~事案~
静岡地検は、窃盗の疑いで逮捕、送検されていた静岡県静岡市内の男性を不起訴処分とした。
地検は、理由については明らかにしていない。
男性はJR静岡駅北口ロータリーで寝ていた男性会社員のかばんから財布とカードケースを盗んだとして、静岡中央警察署などに逮捕されていた。
(静岡新聞「窃盗疑い逮捕の特支教諭不起訴 静岡地検」(2023/11/7)」を引用・参照の上、適宜修正。)
~窃盗罪における占有について~
(窃盗)
第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑法235条(窃盗罪)は、他人の意思に反して他人の物の占有を侵害することを処罰する趣旨の規定です。
詐欺罪等の交付罪とは、物の占有の移転が被害者の意思によるかそうでないかといった点で罪質が異なることになります。
窃取罪が成立するには上記の通り「窃取」という要件を満たす必要がありますが、「窃取」とは(他人の意思に反し)他人の占有を侵害することが前提となっていることから、対象となる財物に被害者の占有が及んでいるかが問題となります。
占有とは、財物に対する事実的支配をいい、これは占有の事実と意思から判断されるものと解されています。
本件では、上記事案の事実の存在を前提とするならば、被害者が寝ていることから占有の意思の減弱が認められうるところ、あくまで盗まれた財物等はカバンの中に入っていたわけですから被害者の占有の事実は強固であり、財物の事実的支配は優に認められるものと考えられます。
なお、詳述はしませんが、窃盗罪の成否においては故意の他に不法領得の意思という主観的要件も問題となることに注意が必要です。
~窃盗事件における刑事弁護活動〜
本事案では、被疑者は窃盗の疑いで逮捕されましたが、後に不起訴処分となっています。
我が国の刑事手続では、検察官の起訴裁量(刑事訴訟法248条参照)が広範に認められており、逮捕(・勾留)されたからと言って、必ずしも刑事裁判になるわけではありません。
不起訴処分にも、罪とならず・嫌疑なし・嫌疑不十分・起訴猶予など様々な理由に基づくものがありますが、本件ではその詳細は明らかではありません。
そこで、以下では(最も多いと考えられる)起訴猶予について、窃盗事件の特徴との関連を中心に記述することとします。
窃盗罪は、財産犯(財産を侵害する犯罪)の典型であり、国家や社会とは異なり個人の法益を保護している犯罪類型です。
したがって、被害者との示談の成立の有無が、不起訴処分を獲得するにあたって大きなウェイトを占めることになります。
仮に被疑者に前科・前歴等があったとしても、示談が成立していれば十分に不起訴を得る可能性があるため、起訴前の弁護活動が非常に重要と言えます。
このことは、統計上、窃盗罪で(略式手続を除く)正式裁判として起訴される件数が非常に少ないことからも裏付けられていると考えることもできるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗事件を含む刑事事件全般を専門として扱っている法律事務所です。
窃盗事件で逮捕された方やそのご家族等は、24時間対応可のフリーダイヤル(0120-631-881)までまずはお問い合わせください。
(事例紹介)静岡市清水区の社会福祉法人における業務上横領事件で団体職員の男性らが再逮捕
(事例紹介)静岡市清水区の社会福祉法人における業務上横領事件で団体職員の男性らが再逮捕

静岡市清水区の社会福祉法人における業務上横領事件で団体職員の男性らが再逮捕された事案について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~事案~
静岡市清水区の社会福祉法人から資金を横領した疑いで逮捕された前理事長ら男2人について、警察は2人がさらに約2900万円を横領した疑いで再逮捕しました。
再逮捕されたのは、団体職員の男(52)と静岡市清水区の社会福祉法人の前理事長の男(43)2人です。
警察によりますと、2人は2022年10月から11月にかけて社会福祉法人の口座から関連会社など複数の口座に少なくとも十数回以上送金するなどして、現金約2900万円を横領した疑いが持たれています。
警察は2人が容疑を認めているかどうか明らかにしていませんが、使途不明金は7000万円に上るとみられていて、警察は引き続き金銭の流れを慎重に捜査しています。
また静岡地検は、2人が共謀して同じ社会福祉法人から1500万円を横領したとして起訴しています。
(テレビ静岡「さらに2900万円を社会福祉法人の資金から横領か 前理事長と団体職員を再逮捕 静岡」(2023/12/11)を引用・参照)。
~業務上横領について~
(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
(業務上)横領罪とは、他人から預かった他人の所有物を着服し自らのものにしてしまう行為を罰する趣旨の規定です(刑法252条、253条)。
業務上横領において刑が加重されているのは、多数人との間の委託信任関係を破壊する点で単純横領のそれよりも法益に対する侵害が重大であるからとも言われています。
上記のように業務上横領(253条)の法定刑が「10年以下の懲役」であるのに対し、単純横領(252条)は「5年以下の懲役」と最高刑が半分であるわけですから、「業務」該当性の検討は非常に重要となります。
ここでいう「業務」とは、社会生活上の地位に基づいて反復・継続して行われる事務であって、他人の委託に基づいて他人の物を管理する事務をいうと解されています。
本件では、報道のみでは事実関係が必ずしも明らかではないものの、被疑者らは法人の金銭を保管する事務を行っていたと考えられ業務者に当たると思われます。
~再逮捕事案の弁護活動等~
本件事案では、被疑者らはすでに一部の容疑では起訴されており、余罪の業務上横領が発覚する度に逮捕が繰り返されています。
なお、マスコミ用語でいう「再逮捕」と法律上の「再逮捕」とは異なる概念であり、混同しないよう注意が必要です。
本件のように違う被疑事実で同じ被疑者を再度逮捕することは、法律上は単に異なる容疑で逮捕しただけであり、裁判例(東京地決S47.4.4等)においても厳格な要件が課せられている「再逮捕」(刑訴法199条3項等参照)には当たりません。
以下では、断わりのない限りマスコミ用語でいうところの「再逮捕」(つまり単なる再度の逮捕)の意味で「再逮捕」の語を使用します。
本事案のように余罪が多数見込まれ、再逮捕が繰り返されているような事案ではどうしても身体拘束期間が長引くことが避けがたくなります。
余罪の有無は、起訴後の保釈(刑訴法88条以下)が認められるかの判断にも関わるため、弁護士が接見を繰り返すことも被疑者・被告人の精神面を含めたケアにとって重要となってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、業務上横領事件を含む刑事事件を専門的に取り扱っている法律事務所です。
業務上横領事件で逮捕・再逮捕された方のご家族等は、24時間/365日対応の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までいつでもお電話ください。
静岡県焼津市で横領の疑いで男性を逮捕
静岡県焼津市で横領の疑いで男性を逮捕
静岡県焼津市で横領の疑いで男性が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事案
静岡県焼津警察署は、横領の疑いで会社員の男を逮捕した。
逮捕容疑は昨年10月下旬から11月上旬にかけて、ゴルフ用品などの製造販売を手がける焼津市の会社のインターネットレンタルサービスを利用して借りたゴルフクラブ2本(時価計12万円相当)を、ゴルフ用品買い取り店に売却した疑い。
(静岡新聞「レンタルのゴルフクラブを売却した疑い」(2023/10/19)を引用・参照。)
~単純横領罪とは~
(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 (略)
刑法は、自らが占有している他人の物の所有権(および所有者との間の委託関係)を保護し、これを侵害する行為を罰するための規定を設けています。
その最も典型的な規定が、上記刑法252条が規定する単純横領罪です。
本件の被疑者は、レンタルサービス会社の有する「他人の物」であるゴルフクラブを「占有」しています。
上記条文に明文はありませんが、かかる「占有」は委託関係に基づくものである必要があります(委託物横領罪とも呼ばれるのはそれ故です)。
本件クラブという「他人の物」は、被害者である会社とのレンタル契約に基づく委託関係によって「占有」されるに至っています。
したがって、被疑者による「横領」行為が認められれば、(委託物)横領罪が成立しうることになります。
ここにいう「横領」とは、不法領得の意思を発現する一切の行為を言い、判例は横領罪における不法領得の意思を「委託の任務に背いて、その物につき権限がないのに所有者でなければできないような処分をする意思」と定義しています。
本件では、レンタル契約に基づいてクラブを利用しなければならない被疑者がこれを売却しており、不法領得の意思およびその発現行為があったといえ、(委託物)横領罪が成立するものと考えられます。
~逮捕を避けるための弁護活動等~
本件では、被疑事実となっている行為は、逮捕から約1年前に行われています。
逮捕されてしまえば、その身体拘束によって決して小さくない事実上の不利益(有職者であれば仕事への悪影響)を被ることになってしまいます。
では本件のように、犯罪行為を行ったとされる時期と逮捕との間にタイムラグがある場合、逮捕を避けることはできなかったのでしょうか。
このとき、まずもって思い付くのは、自首し自ら犯罪行為を申告することです。
そこで自首についての規定を見てみると、「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる」(刑法42条1項)とされています。
自首による法律上の効果は、任意的な「刑」の「減刑」であり、逮捕されない等とはどこにも書かれていないのです。
逮捕回避のために警察へ自首したら、そのまま逮捕されてしまったなどという事例も少なくありません。
つまり、自首(事件発覚前の出頭行為)にはリスクが伴うのであり、慎重を期すべきです。
したがって、自首等による逮捕回避を望む場合にも、まずは専門家である弁護士への相談が必要不可欠と言えます(弊所なら初回相談は無料)。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、横領事件を含む刑事事件を専門としている法律事務所です。
横領事件で逮捕されてしまった方のご家族や逮捕を避けたいという方は、24時間対応のフリーダイヤル(0120-631-881)まで今すぐお電話ください。
2項詐欺事件に関する裁判例・判例の紹介
2項詐欺事件に関する裁判例・判例の紹介
2項詐欺事件に関する裁判例・判例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事案
静岡県東部の祭りで露店出店権を不正取得したとして、詐欺罪に問われた指定暴力団員の男と露天商の女の判決公判で、静岡地裁沼津支部は、男に「懲役2年、執行猶予5年」、女に「懲役2年、執行猶予4年」を言い渡した。
判決によると、両被告は2022年6~11月、富士宮市の三つの祭りで共謀し、暴力団関係者が実質的に経営する露店であることを隠して主催団体に申し込み、出店権利をだまし取った。
(静岡新聞「2人に有罪判決 露店出店権不正取得」(2023年4月28日)を引用・参照。)
~2項詐欺罪について~
(詐欺)
第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
刑法246条(詐欺罪)は、人を欺き錯誤に陥れ、被害者からその意思に基づいて財物や利益を交付させる行為を罰する趣旨の規定です。
2項詐欺罪(刑法246条2項)とは、詐欺行為によって財産上の利益を得ることによって成立する罪であり、近年では「人を欺いて」(欺罔行為とも呼ばれます)という要件の判断が極めて重要になっていると言われています。
判例が定義するところによると、「人を欺」く行為とは、交付の基礎となる重要な事項を偽る行為をいうと解されています。
このような行為によって、人を錯誤に陥らせ財産上の利益を得ることによって2項詐欺罪は成立することになります。
本事案では、報道内容のみからは必ずしも明らかではないものの、主催団体とって出店希望者が暴力団関係者であるか否かは露店を出店する権利を与えるか否かの判断に当たって重要な事項と判断されたと考えられます。
したがって、そのような「人を欺」く行為によって、出店権という「財産上……の利益」を得ることは2項詐欺罪に該当することになるでしょう。
~詐欺事件における裁判実務~
もっとも、注意すべきなのは暴力団員であること等の身分を隠していたからといって常に詐欺罪に当たるわけではないということです。
この点に関しては、平成26年3月28日(刑集68・3・582、刑集68・3・646)という同日に下された2つの判例が極めて重要です。
後者の判例では被告人に有罪判決(懲役1年6月、執行猶予3年)が言い渡されたのに対し、前者の判例では無罪判決が言い渡されています。
両者は同じく暴力団員がその身分を隠してゴルフ場を利用したというケースであるにも関わらず、何故結論を異にしたのでしょうか。
前者のケースでは、当該ゴルフ場では必ずしも暴力団員排除のための措置が徹底されていたとは言い難く、また周辺のゴルフ場でも同様であったことから、暴力団員であることを秘してゴルフ場を利用したことは一般的に見てそもそも「偽る行為」に該当しないとされ、被告人の行為は詐欺罪を構成しないと判断されています。
このように詐欺罪の成否を検討するにあたっては「人を欺」く行為といえるかどうかという要件の該当性において、(重要事項性のみならず)極めて専門的な判断が必要となる場合も存在します。
したがって、詐欺事件においても刑事事件に関する専門性を有した弁護士のアドバイスが不可欠なのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
詐欺事件で逮捕・起訴された方のご家族等は、年中無休のフリーダイヤル(0120-631-881)までお早めにご連絡ください。
【ニュース紹介】名古屋市北区で起きた詐欺事件
【ニュース紹介】名古屋市北区で起きた詐欺事件
今回は、名古屋市北区で起きた詐欺事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。
【ケース】
故障した車について実際には運んでいない距離を運んだなどとうその申告をして、保険金をだまし取ったなどとして名古屋市の25歳の男が逮捕されました。
詐欺などの疑いで逮捕されたのは、名古屋市北区の元ロードサービス業・(中略)容疑者(25)です。
警察によりますと(中略)容疑者は2022年8月、岡崎市内で男性(48)から車の修理を依頼された際に、実際には行っていないレッカー移動の費用などを保険会社に申告し、保険金14万4000円をだまし取ったなどの疑いがもたれています。
警察は(中略)容疑者の認否を明らかにしていません。
(中略)容疑者は2022年6月からの半年間に、249件の依頼を受け、1400万円余りを売り上げていて警察は、余罪についても調べています。
(令和5年6月1日メ〜テレ 「実際には行っていないレッカー移動の費用など申告か 保険金をだまし取ったなどの疑い 男を逮捕」より引用)
【保険金詐欺】
ケースはいわゆる保険金詐欺をしたことで男性が逮捕されています。
保険金詐欺は法的な表現ではなく、保険会社に対して事故や災害の被害にあったかのうように装い、保険金を騙し取る手口の詐欺事件の通称になります。
保険金詐欺に適用されるのは詐欺罪であり、詐欺罪が定められた条文は以下の通りになります。
刑法第246条第1項
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
詐欺罪が成立するためには次のような一連の流れが必要です。
まず犯人が人を欺く行為をし、相手方がその行為によって財物の交付や財産上の利益を求める際の判断基準となる重要な事項に関して錯誤(思い違い)が発生し、その状態で財物を交付、または財産上の利益を犯人または第三者が得ます。
この流れが因果的につながって存在していることが詐欺罪には必要です。
そのため紹介したニュースは男性がレッカーでの移動があったと保険会社を騙し、保険会社は錯誤が生じた状態で保険金を交付しているため、詐欺罪が適用されています。
【会社との示談交渉】
詐欺罪は罰金刑が定められていないため、起訴されれば裁判になる可能性があります。
それを避けるためには被害者との示談交渉はほぼ必須となります。
そのためにも被害弁償をする必要がありますが、被害者が個人ではなく会社などの法人である場合、弁護士を通さないと示談交渉に応じてもらえないというケースも存在しています。
速やかに示談交渉を締結するためにも、詐欺事件に詳しい弁護士に相談し、弁護活動を依頼することが必要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、詐欺事件を含む刑事事件・少年事件を中心に取り扱う弁護士事務所です。
弁護士が逮捕された方のもとに直接向かう初回接見サービス(有料)、初回であれば無料で利用できる法律相談などを当事務所では実施しています。
保険金詐欺の当事者となってしまった方、またはご家族が詐欺容疑で逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
静岡市葵区内の書店で万引き 被疑者を逮捕
静岡市葵区内の書店で万引き 被疑者を逮捕
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が静岡市葵区内で発生した万引き被疑者の逮捕事例にいて解説致します。
【事例】
万引き被疑者の逮捕【静岡中央署】
6日夜、静岡市葵区内の書店でコミックを大量に万引きした住居不定、無職の男(23)を逮捕しました。
引用: 静岡県警察ホームページ 事件・事故速報 9月6日「万引き被疑者の逮捕【静岡中央署】」
https://www.pref.shizuoka.jp/police/about/kohomemo/2005898.html
【解説】
1 万引きはなに罪になる?
結論から言いますと万引きは、盗んだ対象や金額に関わらず窃盗罪に該当します。
窃盗罪が成立し有罪となった場合、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。
窃盗罪は刑法235条に次のように規定されています。
刑法235条 (窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 窃盗罪の成立要件
「他人の財物を窃取」すること
「窃取」とは、他人の占有する財物を、その占有者の意思に反して自己又は第三者の占有に移転することを意味します(判例・通説)。
「占有」とは、持ち主に関係なく財物を現実に支配していることをいい、財物の持ち主を指す「所有」とは意味が区別されています。
以上のような「窃取」という行為が一般的に万引きと呼ばれています。
3 今回の事例の場合
今回の事例では、静岡市葵区内の書店のコミックという「他人の財物」を万引き(「窃取」)したことにより窃盗罪が成立しています。
【事務所紹介】
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が静岡市葵区内で発生した万引き被疑者の逮捕事例について解説致しました。
万引き事件のような被害者のいる犯罪では、被害者との示談や被害弁償をしたか否かが、警察の捜査、検察官の起訴・不起訴の判断、裁判所の執行猶予や減刑の判断に大きな影響を及ぼします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
万引き事件の経験も豊富な弁護士が所属しております。
とりわけ書店での万引き事件については、昨今の出版業界の厳しい現状もあり、厳しい刑事処罰を求める店舗が多く、「本社の方針で示談はしないことになっている」「被害品の買取には応じない」などの姿勢を示される場合が多く、弁護人は被疑者の反省の意思や手続きの流れ、示談の内容などについて丁寧に説明を行い、示談を前向きに検討して頂くよう示談交渉を行うことになります。
ご家族が警察に逮捕されてしまった方や、刑事事件を起こしてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
逮捕され身柄が拘束されている場合には、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。
24時間365日受付中のフリーダイヤル(0120-631-881)
少年が特殊詐欺事件で逮捕
少年が特殊詐欺事件で逮捕
静岡県清水市にて少年が特殊詐欺事件で逮捕されてしまったという報道について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が検討いたします。
事案
清水警察署は、詐欺の疑いで御殿場市の無職少年A(17)を逮捕した。
逮捕容疑は、何者かと共謀して静岡市清水区の無職女性(73)宅に区役所職員や金融機関職員を名乗って「健康保険料の戻りがあるため振り込みたい」「キャッシュカードが古く作り替える必要がある」などと電話をかけた後、金融機関職員を装った少年が女性宅を訪れ、キャッシュカードをだまし取った疑い。
同署によると、不審に思った女性が金融機関に確認し詐欺と発覚した。
(静岡新聞「カード詐取容疑 御殿場の17歳少年逮捕 清水署」(2023913)を引用・参照。)
~何者かとの共謀による特殊詐欺~
本事案では、被疑者である少年が共犯者と共謀し、健康保険料の返戻金が得られるなどと嘘をつき高齢の被害者からキャッシュカードをだまし取った行為が詐欺罪にあたるとして逮捕されるに至っています。
刑法は、246条1項において「人を欺いて財物を交付させた者」を、詐欺罪として処罰する旨の簡素な規定を置いています。
上記規定の文言のみからは必ずしも明らかではありませんが、詐欺罪が成立するためには「欺罔(ぎもう)行為→錯誤→交付行為→受領行為→財物の移転」という経過を辿る必要があると解されています。
いわゆる特殊詐欺では、架け子が「欺もう行為」を行い、これによって「錯誤」に陥った被害者から、受け子が「交付行為」を受けて目的の財物を「受領」するなど、1個の詐欺行為を共謀(刑法60条)して行うことに特徴があります。
本事案でも、氏名不詳者が区役所職員や金融機関職員を名乗って「健康保険料の戻りがあるため振り込みたい」「キャッシュカードが古く作り替える必要がある」などと電話をかけるという「欺もう行為」を行い、これによって被害者は上記事項につき「錯誤」に陥っています。
そして、その後(のちに逮捕された)少年Aさんが金融機関職員を装い被害者宅を訪れ、錯誤に陥った被害者からキャッシュカードの「交付」を受け、もって「受領行為」を行い「財物の移転」が完了しています。
このような行為を共謀(刑法60条)して行っている以上、直接には「欺もう行為」等を行っていない受け子である少年Aにも詐欺罪が成立しうることになります。
~弁護士による逮捕された方への接見~
逮捕されてしまった場合に、まず何よりも重要なのは早期の弁護士による接見です。
刑事訴訟法は、「身体の拘束を受けている……被疑者は」、「弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者」と「立会人なくして接見」することができる旨を定めています(39条1項)。
つまり、逮捕直後の捜査段階において被疑者と接見できるのは、原則として弁護士だけであり、一般の方は接見(面会)することはできません。
したがって、逮捕されてしまった場合には、その不利益(少年であれば学校生活に対する事実的な影響を含む)を最小限化するためにも、いち早く弁護士による接見を要請することが肝要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺事件を含む刑事事件のみを専門にしている法律事務所です。
詐欺事件で逮捕されてしまった方のご家族等は、24時間対応可のフリーダイヤル(0120-631-881)までまずはお問い合わせください。
【年金不正受給】窃盗・詐欺事件の裁判例等を紹介
【年金不正受給】窃盗・詐欺事件の裁判例等を紹介
年金の不正受給に関する窃盗・詐欺事件の裁判例等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事案
死亡した親子の年金458万円を不正に引き出したとして、窃盗と詐欺の罪に問われた被告人に対し、静岡地裁浜松支部は「懲役3年6月」の判決を言い渡した。
判決によると親子が亡くなった後、共犯者と共謀し、親子の口座から現金を繰り返し引き出した。
また、掛川市と愛知県豊橋市の自動車販売会社3社から車3台(販売価格約325万円)をだまし取った。
被告人は同親子の死体遺棄容疑で逮捕されたが、嫌疑不十分で死体遺棄罪では起訴されていない。
(中日新聞「年金不正引き出し、懲役3年6月判決 地裁浜松支部」(2021/1/21)を引用・参照。)
~年金の不正引き出し等の罪責について~
(窃盗)
第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(詐欺)
第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
本事案では、被告人と共犯者が共謀し、死亡した親子の口座から現金を繰り返し引き出した行為に関する罪責が問われています。
一見すると詐欺のような事案に思えますが、上記行為は窃盗罪に該当することになります。
窃盗罪とは、他人の意思に反して他人の財物の占有を移転させる犯罪です。
本事案では、何ら権限もないのに無断で死亡した親子の口座から現金を引き出しており、これはその財物の占有を占有者の意思に反して自己(又は第三者)に移転させていることから「窃取」行為に当たることになります。
ここで注意すべきなのはここで窃盗の客体となる現金という「財物」を占有しているのは、銀行(正確には銀行内の現金の占有権原を有する支店長等)であるということです。
したがって、本事案では銀行を被害者として上記行為に窃盗罪が成立することになります。
なお、本事案で詐欺に問われているのは、上記行為とは別に自動車販売会社から自動車を騙し取った行為であり、これが詐欺罪に該当することは比較的明白でしょう。
~年金不正受給事件における弁護活動等~
本事案では、被告人に対して「懲役3年6月」という実刑判決が下されています。
このような執行猶予なしの実刑判決が下されるケースと執行猶予判決となるケースには、どのような違いがあるのでしょうか。
以下では、年金の不正受給に関する他のケースを紹介します。
死亡した母親の死亡届を提出せず、年金約130万円を不正に受給したとして、死体遺棄および詐欺の罪に問われた被告人に対し、静岡地裁沼津支部は「懲役2年4月」「執行猶予3年」の判決を言い渡しています(静岡新聞「母の遺体を自宅に放置 年金不正受給に有罪」(2022/11/9)を引用・参照)。
本事案と執行猶予の付いた上記のケースでは、年金の不正受給に関し被害額が大きく異なるという点がまず挙げられるでしょう。
また、本事案では、別途詐欺行為がなされており、死体遺棄では不起訴になっているとはいえ、別の主体に財産上の法益侵害を生じさせている点もまた量刑を異にした相違点といえるでしょう。
このように一口に年金にまつわる不正受給事件といっても、事案により量刑は様々であり、専門知識と経験を有する弁護士によるアドバイスが必要不可欠といえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗・詐欺事件を含む刑事事件のみを専門にしている法律事務所です。
窃盗・詐欺事件で逮捕・起訴された方やそのご家族等は、24時間いつでも対応可のフリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。
静岡県裾野市で万引き(窃盗)から暴行ふるって事後強盗罪
静岡県裾野市で万引き(窃盗)から暴行ふるって事後強盗罪
万引き(窃盗罪)などの犯罪が発覚して逃走するために暴力を振るった場合、非常に重大な事後強盗罪へ発展する可能性とその刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事件例】
静岡県裾野市在住の無職Aさん(54歳)が、夜遅くに市内のス―パーで食料品等を万引き(窃盗)したところ、店員Vが万引き(窃盗)に気付いてAさんに指摘し、Aさんを取り押さえようとしたところ、Aさんはポケットから折りたたみナイフを取り出して、Vさんの腕を浅く切りつけ、Vさんが身を引いたことに乗じて駐車場に止めてある自動車で逃走しました。
Vさんは、すぐに静岡県警裾野警察署に被害を訴え、警察は事後強盗致傷罪の疑いでAさんの行方を追っています。
(※フィクションです)
上記刑事事件例は、令和元年12月15日、千葉県四街道市のコンビニエンスストアで、万引き(窃盗)して逃げた男が、追いかけてきた店員の男性を刃物のようなもので刺した事後強盗事件をモデルにしています。
警察によると、15日午後4時すぎ、四街道市のコンビニの女性店員から「万引きの犯人が逃げようとしている」と110番通報があり、被疑者は、商品を盗んで逃げ、追いかけた男性店員が店の外で捕まえようとしたところ、突然、被疑者が店員の上半身を刃物のようなもので刺したとのことでうが、幸い、刺された店員は、病院に搬送されたが命に別条はないとのことです。
逃げた被疑者の男は60代から70代くらいで、警察は防犯カメラの映像などをもとに、逃げた男の行方を追っています。
【強盗と事後強盗】
通常、「強盗」とは、暴行または脅迫を用いて他人が反抗することができない状態にさせ、その反抗抑圧中に財物を奪うことを意味します。
強盗における暴行または脅迫は、社会通念上、客観的に被害者の反抗を抑圧するに足りる程度のものである必要があるとされており、逆に、個々具体的事案における被害者の主観を基準とするものではないとされています(判例)。
上記刑事事件例は、通常の強盗とは異なり、万引き(窃盗)犯が、店員や・警備員・保安員などの追及を逃れるために暴行を加えて財物を奪ったという事案であり、これは刑法第238条の事後強盗に該当します。
具体的には、窃盗を行った者が、財物を得た後で取り返されることを防いだり、逮捕を免れたり、罪跡(証拠)を隠滅するために、暴行又は脅迫を加えた場合、通常の強盗と同じ罪となります(事後強盗、刑法第238条)。
判例によれば、窃盗罪の犯人が、犯行を目的して追跡してきた者による逮捕を免れるために暴行を加えた時、事後強盗罪が成立するとされており、窃盗の既遂後、窃盗現場から1キロほど離れた場所において、窃盗から30分ほど経過した後に、犯人を追いかけてきた被害者に対して、盗品を取り戻されまいと暴行を加えた場合にも、全体から見て、窃盗の機会の延長線上で行われた暴行と言えると判断し、事後強盗罪の成立を認めた判例もあります。
さらに、事後強盗の特徴として、特に店員、警備員や保安員に対する事後強盗のように、財物の所有者という窃盗罪の被害者と、暴行または脅迫を受けた被害者が異なるケースがあります。
当初は強盗罪(事後強盗)の疑いで刑事事件化または逮捕されていた場合でも、例えば暴行被害者に対する示談が成立して、被害届の取下げや刑事処罰を求めない旨の合意を得た場合には、検察官は罪状を窃盗罪に切り替えるケースも見受けられるため、重大犯罪である事後強盗で刑事事件化または逮捕された場合には、刑事事件の経験豊富な弁護士に速やかに弁護活動を開始してもらうことが何よりも大切です。
静岡県裾野市で万引き(窃盗)から暴行して事後強盗罪で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
静岡県静岡市で大学生が給付金詐欺で逮捕
静岡県静岡市で大学生が給付金詐欺で逮捕
給付金詐欺等に加担した場合の刑事手続とその刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
<事件例>
静岡県静岡市在住の大学生A(22歳)さんは、お小遣い稼ぎのため、給付金詐欺グループに参加し、給付金申請役をリクルートする活動を行っていたところ、静岡県警静岡中央警察署の摘発によって詐欺罪の疑いで逮捕されました。
その後、裁判所によって10日間の勾留決定が決まり、両親を含む第三者の面会を禁止する接見禁止命令が下されました。
Aさんの両親は、面会をしたくてもAさんと面会することができず、刑事事件に強い弁護士に弁護を依頼するつもりです。
(フィクションです)
【社会不安の増加に比例して増加する詐欺罪の財産犯罪】
上記刑事事件は、令和2年11月、新型コロナウイルスの影響で収入が5割以上減った事業者らに現金を支給する国の持続化給付金を詐取したとして、広島県警が男6人を詐欺罪の疑いで逮捕した事件をモデルにしています。
不正受給に加担した県内の大学生らが少なくとも100人に上り、被害額が1億円を超えるとみられています。
なお、この6人のうち5人が別の詐欺罪の余罪で再逮捕されています。
捜査関係者によると、逮捕された6人の関係先の家宅捜索でパソコンや携帯電話などを押収、解析した結果、大学生ら100人以上が勧誘され、不正受給に加担した疑いがあることが判明しました。
6人は、大学生らに送らせた運転免許証などの個人情報を悪用し、前年より売り上げが5割以上減った個人事業主と偽るための書類をそろえ、6~8月に中小企業庁のホームページから大学生らの名義で給付金を申請し、それぞれ100万円を入金させていたとみられています。
不正受給した100万円のうち、大学生らの大半は報酬として約10万円を受け取り、残りを6人が分配していたと調べが進んでします。
【昨今の特殊詐欺の傾向】
特殊詐欺被害の実態が十分に周知されてきた現在、捜査機関による取締の強化や厳しい処罰が行われていますが、特殊詐欺被害の件数は未だに若干の増加傾向にあるようです。
特に、集団による特殊詐欺グループにおいて、受け子や出し子として最前線で犯行を行う者が、未成年者または20代半ばまでの若い年齢層であることが非常に多く、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所においても、多くの法律相談や初回接見のご依頼を頂いております。
そして、そのような特殊詐欺グループの実態として昨今問題視されている点として、特殊詐欺の人員を調達する「リクルーター」と呼ばれる者が、地域の不良グループや少年の通う学校の他生徒に影響を及ぼして、立場が下の者に対して特殊詐欺への加担を勧誘したり、強要したりするケースがあります。
特に、特殊詐欺に加担することを拒否したり躊躇する者に対して、暴力的な言動で強要したり、時には暴行を振るうこともあり、そのような背景から暴行罪、傷害罪で立件した例も見受けられます。
教育心理学的には、特に若者は、他者へ同調して人間関係の安定を図る傾向が強く、特に立場が上の者に対して強く反対することが難しいとされており、地域的なネットワークから疎外されるという強迫観念もあり、意にそぐわないまま特殊詐欺に加担してしまう懸念が強く、このような特殊詐欺の事例では、より一層若者や少年の立場を効果的に代弁することができる、刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士に依頼することが大切です。
静岡県静岡市で給付金詐欺等の特殊詐欺で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。
« Older Entries Newer Entries »